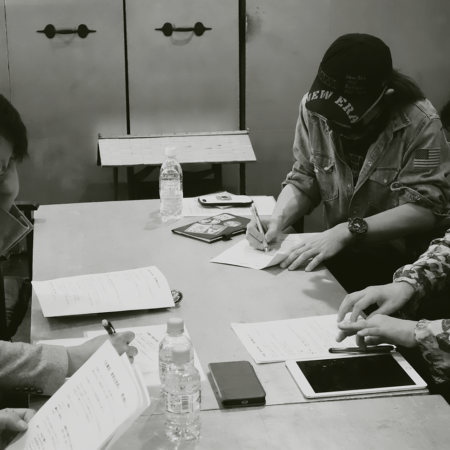SPECIAL
特集
【動画】文楽とシューベルト〈前編〉
意外に思えるコラボの背景とは?
文楽とシューベルト?意外に思われるコラボレーションが、一体どのようにして生まれたのか、その秘話と制作の舞台裏をたっぷり伺います。
出演:
豊竹呂太夫(文楽)
河野克典(バリトン歌手)
渡部玄一(チェリスト)
小川榮太郎(文芸評論家)
――企画が持ち上がった経緯とは?
小川榮太郎(以下、小):この企画はどのような経緯で立ち上がったのでしょうか?
豊竹呂太夫(以下、呂):これは実は河野さんが僕に持ってきてくれた企画なんです。
河野克典(以下、河):僕は歌を歌っています。歌といえば皆さんオペラをすぐに想像されると思いますが、声楽にはオペラだけではなく宗教曲や歌曲という世界もあります。
歌曲は大体が小さな規模のもので、長くても4~5分です。その中でもドイツ歌曲は、ゲーテやシラーといった大文豪に触発されて作曲家が音楽を作っていきました。
僕はオペラも歌いますが、歌曲に非常に魅力を感じています。ドイツ語の歌曲を日本人のお客様の前で演奏する際に、どのように表現すればより伝わるかな、ということは常々考えていました。
「言葉はどのようにして音楽と結びついたのか?」と考えた時に「日本語で歌曲をやったらどうなるのか?」と考えるようになり、
有名な『魔王』を日本の伝統芸能である浄瑠璃でやったらどうなるのか、ということを呂太夫さんに提案して、一緒にやってみませんか、とお声がけいたしました。
浄瑠璃の『魔王』との比較をもって、お客様が今一度歌曲の楽しみ方を知っていただければ、と思いました。
小:河野さんからその話を伺った時にどのように思われましたか?
呂:嬉しかったですね。やはり現代を生きている人たちに伝統芸術をアピールすることは大事ですからね。
僕はゴスペル文楽という新作の人形浄瑠璃をライフワークとしてやってきました。文楽が他の色々なジャンルとコラボすることに関しては非常にやぶさかではないと思っています。
今回、河野さんからこのようなお話しを頂いて、これはいいなあと思いました。
ただ、ゲーテの『魔王』を文楽にするには、練り直さなきゃいけないと思いました。それが結構大変なんですよ。
まずはゲーテのことを色々学びました。ゲーテがこれを書いた当時の時代背景などを研究しました。
しかし、なかなか文章がまとまらないんです。魔王を鬼にしてみたり、子供を「若」と表現したり、「津津たる夜の道…」とか「翔りゆく…」などと言葉を組み立ててみたり、試行錯誤しました。
――シューベルト『魔王』を文楽にする苦労
小:『魔王』は、確かに浄瑠璃と同じで、一人の歌い手が何人かの登場人物を声音を変えて演じる作品ですからね。
呂:そうなんです。「(魔王の声で)若よ、聞こえるかい?」「(子供の声で)父上!鬼が!」「(父親の声で)違う、息子よ、あれは柳の枝が揺れているだけだ」
といったふうにやらないといけない。この日本語の文章を作るのにものすごく時間がかかりました。
同時期に私は伊勢神宮の外宮に特設の広場を作って行う『にっぽん文楽』という公演をやってたんですが、『魔王』の締め切りがその公演の翌々日で。
ですので伊勢神宮の公演の準備をしながら『魔王』を書いてたんですが、なかなかまとまらないんです。
河野さんからは「作品ができたら送ってください」ってずっと言われてたんですけど、伊勢で泊まってたホテルでようやく書けて。すぐに河野さんに送りました。
自分としてはあまり自信がなかったんですけど、それを見た河野さんが「いい!これで私は成功を確信する!」とおっしゃったのです。
嬉しかったですね。それが自信につながって、伊勢神宮の楽屋で三味線の竹澤團吾くんと二人で作曲したんです。
小:後で三味線の曲をつけていくわけですね。
呂:二人で考えていくんですが、これも大変で、締め切りギリギリに(笑)。
小:できあがった浄瑠璃の『魔王』にどういう印象を持ちましたか?
河:もともとのシューベルトの『魔王』は、ピアノの連打で馬の蹄を表現していたり、語り手、魔王、父親、子供の4役を一人で歌い分けるのが特徴の楽曲です。
ピアノの伴奏があるからこそ5分間にまとまるんですが、それを文楽にするとどうなるのかなと思っていました。
ドイツ語の原詩を僕が訳したものをお渡しして、大まかなイメージだけはお伝えしましたが、ほとんど呂太夫さんにお任せで作っていただきました。
できあがったものに「これだ!」と思いました。
小:私はコラボレーションというものを積極的に受け取っています。実験がうまくいってもいかなくても、すること自体に意味があるものだと思っています。
伝統芸能に根ざしている呂太夫さんだからこそ、新しい試みに対して多くの深い答えが出せたという面があるのではないかなと感じています。
渡部さんはここにチェロ独奏で加わってきますね。
――異色のコラボは他にもあるけれど…
渡部玄一(以下、渡):私はお二人と共演する以前に、お二人がコラボされた公演に伺っていたんです。
私は以前から呂太夫さんとご交流させていただいていて、呂太夫さんの関係者としてこの公演を観に行ったら、クラシック関係の知り合いとばったり会って「なんでここにいるの?」なんて言われたりしましたが(笑)。
私は友人にお能の人などがいたこともあり、これまで様々な異ジャンルのコラボレーションを観てきたんですが、基本的にはあまり成功していないなと感じていました。
しかしながらこの公演では、河野さんはすばらしいリートを、呂太夫さんは並列して全く別のものを観せてくれて、
それぞれが邪魔しあったりせず、共通する感動もあり、違いも感じることができて、すごく良かったです。
まさかそれに私を付け加えさせていただくなんて思わなかったんですけど(笑)。
文楽は、ストーリーと音楽がひとつの世界を作っていきますよね。どちらかというと音楽のほうがストーリーに寄り添う形かと思いますが、クラシック音楽の場合は音楽自体で完成されていないといけない。
私が今回演奏する黛敏郎さんの『BUNRAKU』という曲は、クラシック音楽をしっかり極めた人でないと書けないような構成でありながら、
文楽の会場に行って太夫さんの声や三味線の音が聴こえてくるような作品です。外国でも評価が高く、ペータース版という海外の楽譜出版社でも出版されています。
呂:河野さんが、チェロの『BUNRAKU』という曲がある、といってくれてプログラムに組み込むことになりました。
小:それぞれの出会いによってこの企画ができたんですね。
呂:はい。河野さんも渡辺さんも、文楽のファンで、非常に造詣が深く、文楽に対して愛情を感じていただいています。
(おわり)